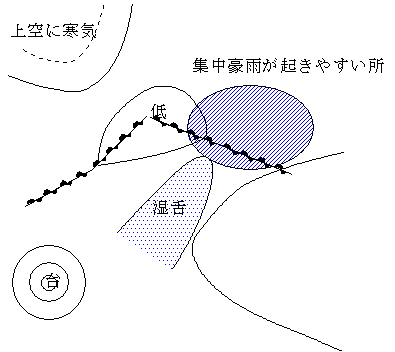
第16章 気象災害
| 目次 | |
| 1. | 気象災害 |
| 2. | 集中豪雨 |
| 3. | 竜巻とダウンバースト |
| 用語と補足説明 | |
| このページの参考となるサイト | |
1.気象災害
梅雨時の長雨は洪水などを起こすばかりではなく、東北地方などでは冷夏(東北地方の太平洋側では冷たい東風=やませが吹く)を引き起こすことにもなる。日照不足で農作物の生育が悪くなることもある。逆に梅雨時に雨が十分に降らないと、水不足(渇水)を招くこともある。
また台風や低気圧がもたらす大雨がある。これより局地的ではあるが短時間に大量の雨が降ることがある。気象庁の正式な用語ではないが、マスコミ等では「集中豪雨」といわれている。集中豪雨は梅雨の末期に多い。冬の日本海側では大雪による被害が出ることもある。
台風や発達した低気圧(温帯低気圧)による、暴風、高波、高潮の被害もある。
さらに、竜巻や雷雨などによる被害もある。
2.集中豪雨
集中豪雨という言葉は正式な気象用語ではないが、マスコミなどではよく使われている。この言葉は、1957年7月25日の諫早での豪雨以来使われるようになったらしい(1958年7月1日の島根県浜田市付近の大雨のときという説もある)。このときは、1時間に最大1000mmくらいのすさまじさだった。全国で死者不明739名の犠牲者が出ている。
1982年7月23日〜24日、長崎では最大1時間に187mm(1時間に30mm以上だとバケツをひっくり返した感じの雨)、2日間で400mm以上(1年の降水量の1/4)の雨になった。この集中豪雨で、全国で死者・不明者345名の犠牲者が出た。このときの119番の交信記録はこちら。
こうした豪雨では、中小河川がいきなり水かさを増し、土石流を引き起こすこともある。
高温多湿の空気中の水蒸気がすべて雨になったとしても、雨量にするとせいぜい40mmくらいにしかならない。つまり、集中豪雨になるようなところには、南の暖かい海から水蒸気が湿舌というかたちで、次から次に供給されているのである。
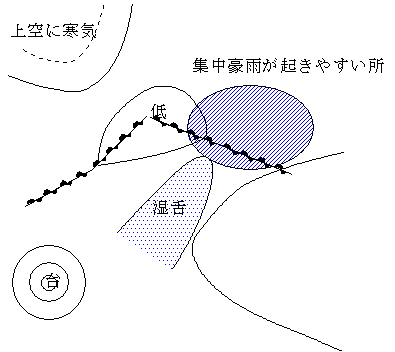
しかし集中豪雨は、天気図上では見えにくい。天気図が表わしているのは100km以上の範囲の現象(マクロな現象という)であり、われわれが体験できる(目で見える)範囲はせいぜい1km程度である(ミクロな現象という)。
集中豪雨はそのちょうど間の1km〜100kmくらいの範囲で起こる現象なのである。この範囲をメソスケールといい、天気予報が非常に難しいスケールなのである(大きさが1000km程度の小低気圧をメソスケールに含めることもある)。
竜巻(アメリカの中南部の陸上ではトルネードという)は激しい空気の渦巻で、大きな積乱雲の底から漏斗状(ろうと状)に雲が垂れ下がってくる。陸上では巻き上がる砂塵、海上では水柱を伴う。その直径は
10

竜巻:http://home.tele2.fr/SurfLePorge/tornade/2.html
ダウンバーストとは積乱雲の底から爆発的に吹き下ろす気流であり、これが地表に衝突して吹き出す破壊的な風をいう。水平規模4km以上のマクロバーストと、水平規模4km以下のミクロバーストがある。マクロバーストは最大風速60m・s-1、ミクロバーストは最大風速70m・s-1を越えることがあるという。電柱や木々をなぎ倒したり、トラックなどを横転させるほどの力がある。とくに、ドップラー・レーダーで捕捉できないミクロバーストは、航空機にとっては大きな脅威である。
なお、ダウンバーストの存在はシカゴ大学の藤田哲也(1920年10月23日〜1998年11月19日)によって発見された(1974年)。彼は1975年のアメリカのケネディ空港における事故がダウンバーストによるものであることも明らかにした。これ以後、各空港にはダウンバースト(マクロバースト)をとらえるためのドップラー・レーダーが設置されることになった。
竜巻とダウンバースト強さは、上の藤田哲也によってF0〜F5の階級に分けられた。これをFスケール(フジタスケール)という。Fスケールについては、たつまき博士研究室の解説を参照。
長崎豪雨の交信記録:1982年7月23日〜24日のときの119番の交信記録が残っている。「気象の辞典」(平凡社、1999年増補版)から抜粋する。こうした大災害のときは、消防もてんてこ舞いでなかなか対応できないということを普段から心得ておく必要がある。
19時46分男:もしもし、あっ、すみません、近所の民家の方の崖が崩れてガス管が、えー、管が破れて今ガスが充満してるんですけれど、それであちこち電話したんですが、自分の処遇で何とかしなさいというばかりで、やむなくお宅に電話したんですが…
消防:あ、ウチのほうもどうにもできないんですね。
男:お宅でもできせん? そんな、ウワー、ガス管の割れているとば(急に怒り出す)、火ばつけば燃えるぞ、つけてみよか今から、
22時20分女:もしもし、もう大水で困っているんですよ…。
消防:どうしたんですか。今長崎はですね、人が生きるか死ぬかしてるんですよ。消防も出尽くしてるんですよ。お宅は生きるか死ぬかしてますか。
23時30分男:あのですねホンコーチのですね、奥山ちゅう所がものすごいひどかとですよ。来てもらえるんですか。
消防:全部出ておりますんで行けないんですよ。
男:(むっとして)結局あれですか、見殺しいうことに?
台風の被害と気象情報:台風による被害は戦前や戦後まもなくのころと比べると確実に減っている。これは天気情報の精度が上がり台風の進路予想がかなり正確になってきたこと、さらに河川の改修が進んだこと、建物の強化がなされてきたことなどがそうして結果を生んだのだろう。例えば現在、台風に限らず、日常的な天気予報でも気象衛星の画像を使った解説がなされている。衛星画像を使った台風の進路予報、さらには天気予報でそれを用いたときの説得力、そしてそれによって被害が軽減できるならば、人の命の尊さを考えると、下の気象衛星の費用(コスト)は決して高くないと思う。
気象衛星にかかる費用:運輸多目的衛星(失敗)旧1号機(打ち上げ+衛星)=256億円、1号機(ひまわり6号、打ち上げ+衛星)=317億円、2号機(予定、打ち上げ+衛星)=296億円。3台の衛星(打ち上げ費を含む)だけで869億円。他に地上施設=1040億円(航空衛星センター(2カ所)509億円、モニター局(6カ所)531億円)。合計1909億円。運輸多目的衛星とは、気象衛星の機能以外に航空管制機能を持つため。ただし、航空管制機能は時代遅れで国際移動衛星機構のインマルサットを利用した方がいいという指摘もある。この気象衛星以外の目的もあるので、気象庁負担分は3台分で274億円。(数値は2005年3月19日朝日新聞朝刊、猪瀬直樹氏の投稿記事より)
気象庁の「おもな気象災害」:http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/whitep/1-2-2.html
気象庁の「防災気象上について」:http://www.jma.go.jp/jma/menu/flash.html
気象庁の「災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料」:http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/saigai_link.html