

国立科学博物館
東京大学総合研究博物館ニュースの塚越哲氏
第2章 生物の進化(1)
| 目次 | ||
| 1. | 生物の大進化 | |
| a.光合成の獲得 | ||
| b.真核生物への進化 | ||
| c.多細胞生物 | ||
| d.性の起源 | ||
| e.生物の大進化のまとめ | ||
| 用語と補足説明 | ||
| このページの参考になるサイト | ||
1.生物の大進化
a.光合成の獲得
酸素を発生するような光合成は、シアノバクテリア(ランソウ、ラン藻)のような原核生物が初めらしい。この無機物から有機物を合成する能力を獲得することによって、生物は自ら栄養を作り出すことができるようになった。それまでは、自然に化学合成された有機物を利用するしかなかった。つまりつねに食糧危機の不安があったわけだ。光合成の能力を獲得したおかげで、自らの体を作ることができるようになったばかりか、他の生物にも利用されることになった。こうして食糧危機は一気に解決する。
光合成は水(H2O)と二酸化炭素(CO2)を原料に、太陽からの光のエネルギーでデンプン(C6H12O6)をつくり、その際に“廃棄物”として酸素(O2)を放出する。
光合成: 6H2O+6CO2+光(エネルギー)→C6H12O6+6O2
呼吸は光合成の逆反応で、デンプンを酸素を使って水と二酸化炭素に分解し、エネルギーを得るものである。
呼吸:C6H12O6+6O2→6H2O+6CO2+エネルギー
しかし、呼吸という能力を獲得する以前は、酸素はその酸化力(有機物を分解する)のために、生物にとっては有害だったはずである。現在の生物にとっても、体内のいわゆる活性酸素が細胞を傷つけるという可能性も持っている。これが、生物の老化の原因の一つだと考えている人もいる。酸素の放出は最初の環境問題でもあったはずだ。
つまり、光合成の獲得は、食糧の安定供給という側面と、酸素という有害廃棄物の放出という側面の、二つの側面を持っている。
シアノバクテリアのほぼはっきりとした化石は西オーストラリアの28億年前のものだという。しかし当然それ以前に、シアノバクテリアは登場していたはずである。
一つの状況証拠が縞状鉄鉱床である。縞状鉄鉱床は海水に溶けていた鉄が酸化鉄になり沈殿してできる。チャートとの互層になっていることが多い。鉄の供給源は、深海底の熱水の噴出孔(ブラック・スモーカー)である。これが海水の循環で浅海に運ばれて沈殿する。
一番古い縞状鉄鉱床は38億年前のものである。ただし、これは光化学的に酸化したものだといわれている。その後も縞状鉄鉱床の沈殿は続くが、22億年前から19億年前に急増し、19億年前からはなくなり、8億年前から6億年まえごろにまた少し沈殿する。深海の海水にまで酸素が十分に溶け込むと、鉄は浅海にまでやってこなくなる。つまり、22億年前から19億年前に大気中の酸素濃度が急増し、深海の海水にまで十分に酸素が溶け込んだものと考えられる。そのころには、大気中の酸素濃度は15%以上、場合によっては現在(21%)よりも多かったかもしれないともいわれている。大気中の酸素濃度の変遷の一つの推定例はこちらを参照。
実際、古い土壌の中の鉄やウランの酸化の程度により、22億年前から19億年前ころに大気中の酸素濃度急増したらしいということもわかる。
シアノバクテリアがつくる構造もある。それはストロマトライトと呼ばれるものである。これはシアノバクテリアが鉱物粒子をくっつけてできる縞状構造である。ただし、似た構造は生物とは無関係にできることもあるので判定が難しいことがある。確かなのは、南アフリカのポンゴラの29億年前のものといわれている。少なくも、このころには光合成を行う生物がいたことになる。
だから、光合成の始まりはたぶんもっと前、今から30億年前以上のことであったのだろう。
 |
 |
| 約5億1000万年前のストロマトライトの化石(アメリカのニューヨーク州) 国立科学博物館 |
西オーストラリア、シャーク湾のハメリンプールの現生ストロマトライト 東京大学総合研究博物館ニュースの塚越哲氏 |
b.真核生物への進化
原核生物(真正細菌と古細菌)から真核生物への進化は、生物にとって非常に大きなジャンプだった。
真核生物の細胞は原核生物の細胞と比べて、まずその大きさが違う。原核生物は数μmしかないが、真核生物は数十μmの大きさである。そして、真核生物の細胞では、遺伝子(DNA)が核に収納されている。さらに真核生物の細胞の中には、ミトコンドリアや葉緑体という小器官を持っている。<2.生物の大分類>で引用した図を下に示す。
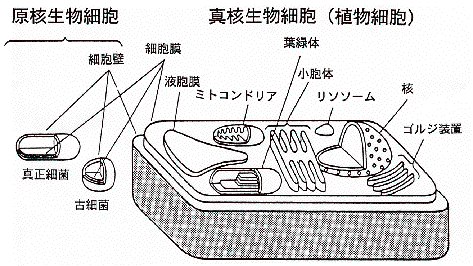
原核生物と真核生物の細胞の比較:東京薬科大学山岸氏のページ
http://www.ls.toyaku.ac.jp/~lcb-7/yamagishi/eukaryotes.html
現在では、原核生物から真核生物への進化は、共生によって行われたと考えられている。つまり、独立に酸素を使ってエネルギーを得る能力を獲得した原核生物(好気的生物)、また光合成の能力を獲得した原核生物(真正細菌、シアノバクテリアに近い?)が、真核生物の祖先になる細胞内に共生し、それらがそれぞれミトコンドリア、葉緑体になったとという共生説が支持を集めている。
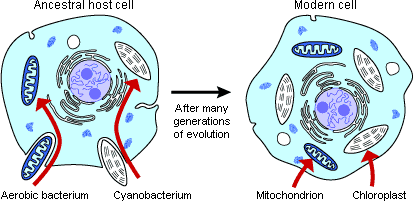 |
Ancestral host cell 受け入れ先となった祖先の細胞 Aerobic bacterium 好気性バクテリア Cyanobacterium シアノバクテリア After many generations of evolution Modern cell 現代の細胞 |
| 共生説:大きな祖先細胞(原核生物)に酸素呼吸の能力を獲得した好気性バクテリアや光合成の能力を獲得したバクテリア(シアノバクテリア)が共生して、真核生物になったという説。 http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/_0/history_24 |
|
実際、ミトコンドリアや葉緑体は独自のDNAを持っている。ただし、現在ではそれ自身のDNAだけでは自分を複製できなくなっている。長い間共生を続けた結果、自分自身のDNAの一部が共生した細胞の核に取り込まれてしまったらしい。
オーストラリアのパルパラの、後の世代によって汚染されていない27億年前の頁岩(けつがん)からは、真核生物起源らしい有機物が検出されている。はっきりとした細胞自身の化石は、19億年前のアメリカやインドの地層から見つかっている。
なお、真核生物(動物、植物)の細胞、細胞内の小器官ミトコンドリアの図はこちらを参照。
c.多細胞生物
十数億年前の地層からそれらしき化石は報告されているが確かでない。はっきりと多細胞生物とわかる化石が出てくるのは6億年くらい前からである。
その中で有名なのが、エディアカラ化石群(5億6500万年前〜5億4300万年前)であろう。最初にオーストラリアのエディアカラから見つかった生物化石群である。その後、世界各地からこの時代の多細胞生物の化石が見つかっている。エディアカラ生物群の生物と、現在の生物の関係、つまり祖先であるかについてはよくわかっていない。
多細胞生物では、形や役割の異なる多くの細胞が組織や器官を作っているのが特徴である。一つの生物ではないが、多くの個体が集まって群体というものをつくることがある。その一つ一つ(個虫)が同じ形をしているサンゴのようなものもいるが、カツオノエボシ(通称電気くらげ、一つのクラゲのように見えるが多くの個虫が集まった群体である)のように、形の異なる個虫がそれぞれの別の機能を持つようになった群体もいる。さらに、個虫の原形質(細胞の中のコロイド状の中身)が互いに連絡氏合うようになるものいる。逆にカイメン(sponge)のように、多細胞生物といっても細胞の分化があまり起きていないものもいる。
 |
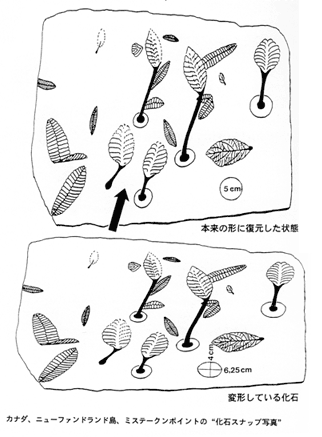 |
| エディアカラ生物群の化石 国立科学博物館:化石の美と科学展 |
左の化石の復元図 国立科学博物館:化石の美と科学展 |
d.性の起源
大腸菌のような原核生物でも接合ということを行い、二つの細胞が遺伝子の交換を行うことがある。しかしはっきりとした雌雄性はない。
はっきりとした雌雄性を持つのは、真核生物だけである。真核生物がいつごろ雌雄性を獲得したのかはよくわかっていない。おそらく、8億年前ころ〜十数億年前ころのことだと思われる。
有性生殖では、ふつうは偶数(ヒトでは46本)の染色体の数が1/2になった生殖細胞(大きくて栄養分を持っているのが卵細胞、小さくて運動性があるのが精細胞)ができ、それが1:1で融合(受精)して再び元の偶数に戻る。つまりこうしてできる子は、雌(母)方からと、雄(父)方からの遺伝子を半分ずつ持っていることになる。
雌雄がなく単純に細胞分裂で増えることができる無性生殖より、雌雄を持った生物が有性生殖をするには、まず雌雄が出会わないとならない。こうして面倒な点を上回るメリットが、(1)進化が速くなる(遺伝子の多様な組み合わせができる)、(2)有害な突然変異(DNAの損傷)を片方の遺伝子で修復できるということだと思われる。
ここまでの進化の大ジャンプが起きたと思われる年代ををまとめたのが下の図である。これらの大進化は地球環境の変化と関係があると思われるが、どのような関係にあるのかはよくわかっていない。
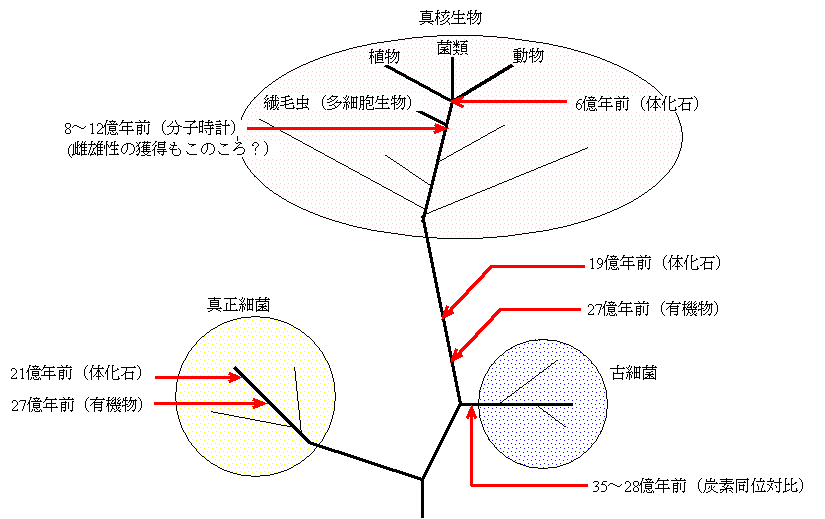
「マクロ進化と全生物の系統分類」(シリーズ進化学1、岩波書店、2004年12月)のp.97の図1を少し変更して簡略化
推定年代の( )内は元となるデータ。炭素同位対比、有機物を参照。また、分子時計はDNAやアミノ酸の分子構造の差異から、どの分岐がいつ起きたかを推定する方法。
共生:別種の生物が相互依存の関係で生活していること。一方の生物が被害を蒙るようなものは寄生という。
共生説:共生説を唱えたのは、リン・マーギュリス(L,Margulis)である。「共生生命体の30億年」(リン・マーギュリス、中村桂子訳、草思社、2000年8月、ISBN4-7942-00991-6、1,800円)に、その考えがまとめられている。この本では、彼女がこの考えを述べた論文が最初に学会誌に掲載されたのは1967年で、当時の名前はリン・セーガンであったことも書かれている。つまり、当時彼女は有名な天文学者カール・セーガン夫人だったのだ。カール・セーガン(アメリカ、1934年〜1996年)については日本惑星協会のページを参照。
マーギュリスは細胞の運動器官である鞭毛(べんもう)も、スピロヘータのような細胞が共生した結果できた器官と考えている。さらに、他の細胞小器官もすべて共生が起源であるという連続共生説を唱えているが、これはあまり受け入れられていない。

リン・マーギュリス
http://www.geo.umass.edu/faculty/margulis/
岐阜大学教育学部地学教室全地球史:http://chigaku.ed.gifu-u.ac.jp/chigakuhp/e-history/html_/eh/index.html